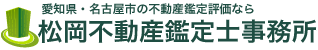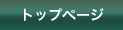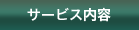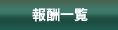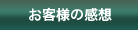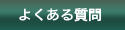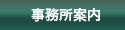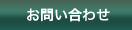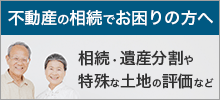Archive for the ‘不動産の価格’ Category
AIによる不動産の査定価格と実際の取引価格
以前、ネット記事にサザエさんの自宅、ドラえもんののび太の自宅、ちびまる子ちゃんの自宅、クレヨンの自宅のAIによる査定価格が出ていました。やはり、東京都区部に住んでいるサザエさんの家は約2億円弱、のび太の家は1億円弱と高額となりました。
ちびまる子ちゃんの家は、静岡県の旧清水市、住みやすい街ではありますが1100万円~1300万円とリーズナブルな査定額でした。
クレヨンしんちゃんの家は埼玉県春日部市、首都圏ではありますが、3000万円弱~3500万円弱、一般的なサラリーマンでも購入可能な金額となりました。
このAIによる査定で、私が実際に購入した不動産の査定を二つやってみました。結果は実際の購入価格よりかなり高めの金額となりました。感想としては、相場より安く買った印象はありますが、やはり高めに試算されています。また、売却を考えている不動産のAI査定をやってみましたが、こちらも高めの査定結果との印象です。
総括ですが、AIによる査定は、ビックデータを活用した査定であり、周辺の取引価格の多少が精度に直接反映します。また、駅距離などの地域性は同じ町内でも違ってきますし、特に土地(形状や方位など)や建物(破損・老朽化)の個別性は一律査定での反映は難しく、相場価格を知る上では有用ですが、現段階では限界はあるのかな、という印象です。
マイナスの不動産価格の内訳
以前、越後湯沢のリゾートマンションの鑑定評価額が10万円というブログを書いたことがあります。需要よりも供給、圧倒的に売り圧力が強い市場では、新築購入価格に関わらず10万円という価格になってしまうようです。但し、実際、成約になった場合の価格は10万円以下、0円かもしれません。
先日、ネットで越後湯沢のリゾートマンションの所有者に、マイナス180万円で購入希望、とのダイレクトメールが届いた、との記事を見ました。ちなみにその金額の内訳は、修繕積立金・管理費の2年分(月額5万円)として120万円(滞納していると仮定)、室内の家具・家電類の撤去費用20万円、室内清掃費・設備修繕費20万円、不動産取得税・登録免許税30万円、合計190万円を不動産価格の10万円から控除して180万円だそうです。
このようなリゾートマンション、間取りにもよりますが小規模のものが多く、家具・家電類の撤去費用20万円と室内清掃費・設備修繕費20万円は高いと思います。但し、所有するだけで管理費として年間60万円かかるとすると、単純計算で3年で元はとれることになりますが。
このような買取業者は、主に中国人向けの販売を目的としてるようですが、短期で転売できる当てがあるのでしょうか。もし、これがビジネスとして成立するのであれば、越後湯沢にリゾートマンション価格も10万円よりは上がっていくものと思われます。
郊外ショッピングモールの隣地の鑑定評価
休日はショッピングモールで買い物するというスタイルが定着した日本、確かに、愛知県内でもイオンモールをはじめ沢山のショッピングモールができました。
特に区画整理事業地内など、新しい街にはショッピングモールができることが多く、周辺にもおしゃれな店舗などもでき、人気の住宅地域になることが多いです。
このショッピングモール隣のマンションに価値なし、との記事を見ました。このような住宅地域はいずれ人気が廃れて人口が減り、また、ショッピングモールが建つような商業地域は住むのに適さない、というのが理由のようです。確かに、休日は人と車の往来に悩まされることになりそうです。
不動産の鑑定評価を行う際、最有効使用に基づく価格を求めることになります。郊外ショッピングモール隣の土地の最有効使用、駅距離、前面道路、容積率・建蔽率、さらには土地の規模や形状から判断することになりますが、マンションを最有効使用とした場合、将来的なことを考えると需要は弱くなるのかもしれません。
隣地境界線と鑑定評価額との関係
建物を建築する場合の、陳地境界線と外壁との距離は民法では50mと定められています。但し、用途地域が第1種低層住居専用地域では、1.0m乃至は1.5m離すよう定められており、良好な住環境は確保されますが、敷地利用率は落ちることになります。なので鑑定評価額(収益価格)は低くなります。
先日、ネットで建物西側の敷地に集合住宅が建築中で、隣地境界との距離が91cm~126㎝と近接している、との記事を見ました。建築中の建物は木造であり、耐火建築物ではないため隣地境界から離した設計にしたと思われます。
今回のような収益物件の場合、敷地の有効利用率はそのまま収益率に反映することになるので、オーナーは少しでも隣地に近づける形で建物を建てることを考えると思います。隣地境界から平均で約1.1m離して建物を設計しており、隣地所有者への配慮はみられるのでは、と思います。
隣地境界との距離ですが、50cm未満で建物を新築される方もあります。今回のケース、これ以上の設計変更は難しいと思われます。
特殊な不動産の鑑定評価
不動産の鑑定評価における収益価格は、更地の場合、最有効使用を前提とした建物を想定し、その不動産から得られる純収益を土地と建物に配分、その土地部分の純収益に還元利回りを考慮して求めることになります(土地建物の純収益から一体の収益価格を求め、その価格から建物価格を控除して求める方法もあります。)。
対象不動産が土地建物の場合は、土地建物一体が生み出す純収益から収益価格を求めるので、鑑定評価額も一体の価格になります。
その収益価格ですが、延べ面積に対する賃貸面積の割合が大きいほど収益は多くなりますから、当然、収益価格は高くなることになります。なので、賃貸に出すことを想定しない特殊な建物の場合、収益を生み出さない面積が大きくなりますし、また、借り手も限定されるため収益価格は低くなることが多いです。
先日、東京の三陽商会のビル売却の記事を見ました。売却額は約117億円(簿価50億円+売却益67億円)、広さは100坪強、自社ビル目的で設計されており、階段とエレベーターが複数設置されているそうです。
このような特殊なビルは、やはり需要が限られ市場性は劣ることが多いです。賃貸を想定して自社ビルを設計することはないと思いますが、やはり汎用性のある無難な設計の方が、収益に出す際は有利だと思いました。
鑑定評価額とオークションの関係
最近、官庁や自治体によるオークション公売が盛んです。最も、財務省は物納などによる不動産を公売、法務省は破産財産を競売しており、共にオークションと同じ理屈で価格が決定しています。
不動産の鑑定評価は、最有効使用(不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用(以下「最有効使用」という。)を前提として把握される価格を標準として形成される。この場合の最有効使用は、現実の社会経済情勢の下で客観的にみて、良識と通常の使用能力を持つ人による合理的かつ合法的な最高最善の使用方法に基づくものである。)を前提に価格が決定されており、こちらもオークションと同じく最も高い価格をもって鑑定評価額となります。
不動産の鑑定評価もオークションも、どんなに価値があっても需要がない又は少ないものは価格が安く、逆に需要があるものは価格も高くなるという市場の原理に合致した方法であることは間違いなさそうです。
不動産の価格は1物4価
今月1日、相続税の路線価が発表されましたが、この路線価より試算される相続税評価額を含めて、不動産の価格は1物4価と言われることがあります。
まず、代表的な不動産の価格として、毎年1月1日時点を基準とする地価公示価格(国土交通省)及び毎年7月1日時点の地価調査価格(都道府県)があります。この地価公示及び地価調査価格は、概ね実勢価格(時価)を表しており、取引等の指標として使われることが多いです。
次に、固定資産税路線価より試算される固定資産税評価額があります。この価格は、固定資産税等の徴収のもととなる価格で、3年に1回評価替えを実施しています。
最後に、実際の市場で取引される価格、実勢価格があります。この価格は市場価格、時価などともいわれ、上記で述べた公的価格を求める際の基礎となる価格でもあります。
不動産の価格は、相続税、固定資産税の徴収及び取引の指標など目的によって使用する価格は違っており、馴染みのない方には少し分かりにくいかもしれません。
豊洲用地訴訟の鑑定評価額
先日、東京都豊洲移転用地訴訟の東京地裁判決がでました。結果は、割高購入は認定したものの、土地の取得は不合理ではなく、住民敗訴でした。
今回、東京都の購入費(取得価格)が約578億円、裁判官は、正常価格は購入費から土壌汚染対策費を引いた額、取得価格は134億円高かったと認定しました。正常価格は約444億円、但し、取得価格との差額が3割程度なので不当な高値ではない、という判断のようです。
不動産の鑑定評価額の高値上限は3割程度まで、という指標と示した今回の判決、今後の用地買収における鑑定評価に影響を与えそうです。
埋蔵文化財の埋まっている土地の鑑定評価
土地の鑑定評価を行う場合、遺跡など埋蔵文化財が埋まっているか否かの地歴調査を行いますが、不動産鑑定士の調査では実際に試掘するわけではなく、市町村の教育委員会などが持っている遺跡マップにて調べることになります。
私も、過去何度かこのような鑑定評価に遭遇したことがありますが、対象地や隣接地、周辺などで試掘・本掘の記録があるか、又は実際に土器などが発見されたかなどを調査しすることになります。
少し前ですが、長崎県の県庁跡地の発掘調査で石垣群が姿を現したそうです。県庁跡地ですので、おそらく事業主体は長崎県だったと思いますが、もし、民間の事業者だった場合、本掘費用は事業者負担になるので大変な負担になります。私が学生だった頃、読売新聞中部本社の社屋で織田家の遺跡が発見され、社屋の建て直しにお金と時間が掛かったと聞いたことがあります。
埋蔵文化財、遺跡として残すことも大切ですが、事業者の負担も軽くする制度を検討すべきだと思いました。
女性が購入したマンションの価格は3000万円台
新型コロナウィルス感染症の影響でリモートワークが普及するにつれて、需要者のニーズが駅距離から広さ、マンションから戸建住宅、などという声も聞かれるようになりました。但し、女性はセキュリティーを重視しマンションを好む傾向が強いようです。
先日、ネットに女性が初めて購入したマンションの価格の4割が3000万円台、との記事が出ていました。おそらく、東京及びその近辺のマンション売買が中心なのでしょうか、結果は高めの価格という印象を持ちました。
マンションの購入、メリットとデメリットがありますが、メリットとして所有する満足感があると思います。自分の家は、自由に模様替え等ができますし、賃貸のように退去を求められることもありません。
もちろんデメリットとして、借入金があればローンの支払いは残りますので、十分な検討の後、購入を決めることが大切だと思います。
« Older Entries Newer Entries »