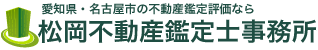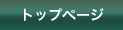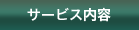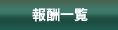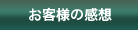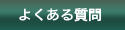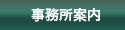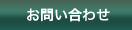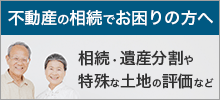Archive for the ‘特殊な不動産’ Category
築約170年の古民家の価格
先日、古民家の鑑定評価額について書きましたが、先日、ネットで築173年の古民家の売り価格が1990万円との記事を見ました。
場所は青森県弘前市、広さは693坪(2290平米)、建物は6LDKの古民家ですが、フルリフォームされており、買い手は手を入れることなく住めるそうです。
ちなみに建物内には、売り主の社長さんが集めたアンティーク家具などの調度品も置かれており、買い主にそのまま譲りたいとのことです。
この古民家が高いか安いかは、人によるかと思いますが、ここまでのリフォームにかかる費用と調度品の価格、そして歴史的価値を考えると、価値のわかる方には安い買い物なのかもしれません。
お寺の鑑定評価額
先日、ネットでお寺を買う富裕層が増えている、との記事を見ました。お寺は全国に約7万4千件程、その内住職のいない空き寺は1万~2万件だそうです。かなりの数ですが、人口減及び檀家の高齢化などでお寺の経営も楽ではないようです。
そのお寺を買うにあたっての価格ですが、お寺を鑑定評価する場合、宗教施設として継続使用するのか、他の用途(簡易宿泊所や合宿所など)に利用するかで価格の種類が違ってきます。前者の場合は特殊価格(一般的に「市場性を有しない」不動産の経済価値を表す価格)、後者の場合には通常の市場価値を有する価格、正常価格を求めることになります。今回のようなビジネス目的の売買の場合は、正常価格として鑑定評価額を決定することになると思います。
お寺の鑑定評価は私も遭遇したことはありませんが、以前、境内地(お寺の境内の土地の一部)を鑑定評価したことはあります。そこはとても大きなお寺の一部で、本堂などの修繕を行う大工さんなどの宿舎として使われていた土地でした。また、知り合いの不動産鑑定士さんは、実際のお城を鑑定評価したそうです。
お寺を利用したビジネスモデル、まだ普及していませんが今後増えていくかもしれません。
ある無人島の価格
昨日は山の価格のことを書きましたが、今日は無人島の価格のお話しです。少し前ですが、ある実業家の方が広さ5万坪の無人島を8500万円で購入した記事を見ました。場所は九州、電気のみ通っているとのことでした。
この方はリタイヤ後、個人的に楽しむために購入したそうです。これだけの広さがあれば、相模湾の初島のようにリゾートとして使用できると思います。
現在は、井戸を掘られて水は大丈夫のようです。自ら島を開発する苦労も全てが楽しみとのこと、素晴らしい方ですね。
ビジネスマン、実業家として忙しく生きてみえた島のオーナー、リタイヤしても力いっぱい生きてみえますね。
レトロな古民家郵便局の鑑定評価額
古民家の鑑定評価、まだ遭遇したことはありませんが、難しい評価になると思います。難しいのは土地より建物、文化的価値のない普通の古民家であれば建物価値はゼロになると思いますが、維持管理がされており、住居として使用可能であれば、建物にある程度の価値を見て、必要とされる修繕費を控除すること建物価格を求める場合も考えられます。
先日、鹿児島県枕崎市の旧郵便局の建物(事務所付住居)が土地付きで100万円で売りに出されたとの記事を見ました。明治37年に建てられたレトロな建物で、1980年代後半まで人が居住していたそうです。ちなみに建物は当時としてはモダンな洋風の造りで、文化的価値があるとのことです。
このような不動産を鑑定評価する場合、土地の価格に加えて建物の価値をどの程度見るかが問題となりますが、記事によると老朽化が激しく、修繕費に少なくても300万円~400万円掛かるとのこと。私がこの不動産を鑑定評価するとしたら、建物価値はゼロ円、文化的価値を考慮して取り壊し費用を考慮しない、という評価方針になると思います。
市民農園利用権付住宅の価格
最近は、趣味で農園を耕す方も増えており、私も昨年まで旧下山村で畑のお手伝いをしていました。そのような方をターゲットにした戸建住宅が売りに出された記事を見ました。
場所は埼玉県春日部市、東武伊勢崎線の最寄り駅から徒歩23分に立地しています。土地は200㎡超、テレワークに対応した書斎とスタディーカウンターを完備しています。その中でも特に特筆すべき点は、市民農園利用権付であること、その地主が栽培等のノウハウを教えるイベントもあるそうです。
市民農園は名古屋でもかなり盛んで、以前、市民農園を廃止して売買に出される方の鑑定評価をしたことがありますが、市の担当者から市民農園の継続をお願いされて困っている、と言っておられました。利用者がとても楽しみにしており、順番を待っている人もいたそうです。
最後にこの分譲住宅の価格ですが、約3000万円弱から3600万円、安いとみるか高いとみるかは人それぞれだと思いますが、私は通勤可能な方で別荘地の気分も味わいたい方にはお手頃な値段だと思います。
用途地域1低専のマンション
市街化区域は都市計画法に基づいて用途地域が定められており、その中でも住居系の用途地域である第1種低層住居専用地域(1低専)は、建蔽率、容積率などが他の用途地域よりきつめになっており、良好な居住環境を有する地域が多いのが特徴です。
1低専におけるその他の規制として、主に10mの建築物の高さ制限がなされており、通常の建物ですと3階建てが上限になります。
先日、ネットで1低専にある4階建てマンションの1階に居住する方が、台風19号で住居が水没し、死亡したとの記事を見ました。このマンションは10mの高さ制限をクリアーするため、1階を半地下にしており、大雨で水が流れ込んだそうです。
建築基準法の緩和の影響もあり増えてきた半地下の住居、水害のリスクを考えると避けた方が無難なようです。
保育園は鑑定評価で嫌悪施設になるか?
先日、お世話になっている方から保育園のことで相談を受けました。内容は、仕事場付住居の近くに保育園の設置が予定されており、その反対運動についてでした。反対者の話では、保育園の設置で地価が10%下がったとの統計がある、との主旨でした。
ちなみに、私は地価が10%下がることは大変なことで、余程の嫌悪施設(火葬場など)が設置された場合だと考えています。おそらく、この反対者の方は、財産評価基準の「著しく利用価値を減じた土地」について10%減額を認める、の文言を引用したのでは、と思います。
以前、小学校の隣の土地建物を鑑定評価したことがありますが、減価はなしと判断しました。子供の声は日中の限られた時間内であり、近隣に悪影響を及ぼすとは考えにくいことが理由です。ちなみに、地価公示などでは、小学校が近いと増加要因なります。
先日、東京都練馬区の保育園の近隣住民が騒音差し止めと損害賠償の請求訴訟で、東京地裁は「騒音は我慢の範囲内」と請求を棄却した記事が出ていました。園側の騒音レベルを抑制する努力も評価したようです。
保育園は、園児の声以外にも、父兄の送り迎えの車の迷惑駐車などの問題はあると思いますが、これは保育園以外でもありえる事象であり、減価は難しいと思います。
但し、鑑定評価は地域性などを個別に判断することになるので、保育園の規模や時間なども考慮して価格は決定することになります。
欠陥マンションの鑑定評価額
耐震性の不足や雨漏りなど、欠陥マンションの問題が増えています。販売会社が大手のディベロッパーであれば、建て替えなどで問題を解決するケースもありますが、中小の不動産会社であれば修繕で済ます、又は裁判で責任を否定するケースもあります。
滋賀県で、耐震性や雨漏りによる瑕疵が発生したマンションが裁判になっているケースがあります。販売会社が施工を請け負った企業を訴えたケースだそうです。
この欠陥マンションの価格ですが、最上階で3800万円だったものが、資産価値50万円まで下落したそうです。減価額はどのように査定したのでしょうか?
区分マンションを鑑定評価する場合、いくつかの手法を使いますが、減価額は、原状回復費用に加えて市場性の減価を加算して求めることになると思います。今回の査定額50万円ですが、買い手が現れてたらこれくらいの価格では?との推定値のような気がします。
欠陥のある住宅は売るのも難しくなるので、購入は慎重に行う必要があると思います。
豪邸の鑑定評価額
一般的な個人住宅ではなく、実業家や旧家の方のお屋敷の鑑定評価することがありますが、非常に難しい評価になります。このような不動産は需要が少なく、特に建物は耐用年数が残っていても取り壊されて更地後、区画割して販売されたり、マンション用地として販売されることが多いことが理由となります。
売主としては、建物にも費用を掛けていますから現状での売買を望むことが多いのですが、そのまま建物を利用する買主は少なく、取り壊し費用分を控除した金額で売買されることがほとんどとなります。
私の遭遇したケースでも、建物の価値はつかず取り壊し最有効での評価となりました。需要の弱い地域でもあり、とても低い評価額になったことを覚えています。
お金をかけた建物が取り壊されるのは辛いですが、代替わりが進んでいくにつれ、このようなケースは増えていくと思われます。
地下埋設物のある土地の鑑定評価
地下埋設物のある土地の鑑定評価は、通常、更地の価格を求めた後、地下埋設物を除去する費用を控除し、埋まっていた物によってはさらに減価(心理的嫌悪感・スティグマ)して求めることになります。
地下埋設物のある土地は、例えば鉄塔敷地の基礎などになると撤去費用が相当な金額になることが多く、場合によっては更地の価格を上回って鑑定評価額がマイナスになることも考えられます。
先日、茨木県筑西市の市売却地にごみが埋まっており、土地購入者の損害賠償として2010万8000円を支払う議案が可決されたとの記事が出ていました。今回の損害賠償額の算定方法としては、鑑定評価と同様に撤去に係る費用の実額を求めることになると思います。
今回のケース、記事に詳細は出ていませんが、実際の算定額をどのように求めたのか興味深いです。
« Older Entries Newer Entries »