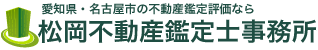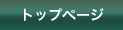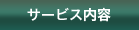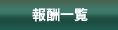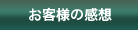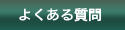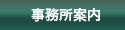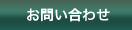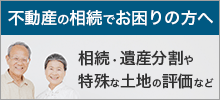Archive for the ‘特殊な土地の評価’ Category
ブロック塀のある土地の鑑定評価
先日、ネットで県が民地のブロック塀を県所有と誤って解体し、損害賠償金220万円を支払ったとの記事を見ました。このブロック塀は、高さ約2.5m、長さ約35m、高さと築年から危険と判断したようです。
ブロック塀は地震で倒壊する可能性があり、事故が相次いだことからフェンスに交換されるケースが多いです。私が子供の頃住んでいた家も、ブロック塀からフェンスに交換しました。
ちなみに解体されたブロック塀は、再設置されたのでしょうか?再設置された場合、損害賠償金220万円は、塀の再設置費用とは別に支払われたのでしょうか?興味深いところです。
今回のようなブロック塀のある土地を現況所与で鑑定評価する場合、ブロック塀の程度(老朽化や倒壊の危険性)から判断し、土地の価格から解体撤去費用を控除して求めることになると思います。
自然災害が多く起こる昨今、ブロック塀に限らず、危険性のある土地の評価は、よりシビアになっていくと考えられます。
旗竿地の鑑定評価
旗竿地とは、間口に対して奥行が長い土地などを分割する場合などで、手前側の画地の側方を通路や駐車場、その奥の土地を建物敷地とするL字型の土地を言います。
建物の建築には建築基準法で2m道路に接する必要があり、旗竿地の間口は2m以上であることが通常ですが、建築基準法が施工される前の古い土地で尺貫法の時代の土地などでは間口2m未満のものも見られます。
このような間口が2m未満の土地ですが、私も鑑定評価で何度か遭遇したことがあります。再建築ができない場合、土地の減価は大きく、価格は安くなることになります。また、鑑定評価の対象となった土地の隣地が間口狭小の旗竿地だったこともあります(その隣地は、間口要件を満たすために境界杭を移動させて越境していました。)。このような悪意のケースはまれですが、旗竿地は間口が2mあるかないかで土地の価格が大きく変わってくるので、所有者も悪いことを考えるのだと思います。
通常の間口2m以上の旗竿地の鑑定評価額は、間口と路地上部分の長さが重要となります。間口が広ければ駐車が可能だったり日照・通風にも有利ですから。このような旗竿地は当然、当然価格は割安になります。日照・通風等に目をつむるのなら道路から奥まっている分静かですから、静かな土地が好きな人にはお買い得に感じるかもしれません。
鉄道施設の鑑定評価
以前、岐阜市及び近郊を走る名鉄市電が廃止された際、その線路敷跡の鑑定評価をしたことがあります。但し、その際は現況線路用地ではないので、通常の宅地として評価を行いました。
先日、鉄道会社の駅舎ビルや線路用地の競売にからむ裁判があったことを知りました。原告の不動産会社が、交渉過程で得た情報を悪用されたと落札した鉄道会社を訴えたものでした。
ちなみに鉄道会社が落札した価格は2億5503万円、競売に負けた不動産会社の価格は落札価格を少し下回る金額だったと思います。
鉄道会社も駅舎ビルや線路敷の適正な価格がわからなかったのでしょうか。上記の交渉過程で悪用された主な情報は、おそらく不動産会社が出した査定価格だったと思います。。
現況線路敷の鑑定評価は、私も遭遇したことはありませんが、もし依頼された場合は、過去の取引事例などから価格を出すことになると思います。とても難しい鑑定評価になることが予想されます。
東京都の築地市場跡地の価格
東京都の築地市場跡地、小池知事の話では都が所有して有効利用する方針でしたが、今回の新型コロナウィルスの対策費による都財政の圧迫で売却する案が浮上し始めました。
築地市場跡地ですが、広さは約23ヘクタール、銀座の徒歩圏であり売却された場合の価格は1兆円との声も聞かれます。最も、コロナ禍の経済情勢が見えない中、これほどの土地に買い手が付くかの問題はありますが。
この築地市場跡地の売却の話が出る一方、従来の方針通り民間に土地を貸し出す方が得との意見もあり、すぐに売却されるか否かは不明のようです。
ちなみにこの土地、売却か貸した方が得かどちらでしょうか?鑑定評価した場合、難しい判断になると思います。
容積率700%の豪邸の鑑定評価
施工の質や品等がよく、延べ面積の広いいわゆる豪邸の鑑定評価は難しい場合が多いです。このような高額な一般住宅を買う需要者が限られますし、類似性の高い取引が少なく、価格を把握することが難しいことが理由となります。
ネットで、東京の皇居前の80坪の豪邸が競売に付されるとの記事を見ました。土地の面積は約80坪、建物は2階建て、1階部分は9部屋あるそうです。ちなみに売却基準値価額は4億5千万円だそうです。
この不動産が存する地域の容積率は700%、鑑定評価でいう最有効使用は現行の一般住宅ではなく高層ビルかホテルになると思います。従って、この不動産の建物は落札後、取り壊されることになると思います。
このように取り壊されることを前提とした鑑定評価上の最有効使用を、取り壊し最有効といいい、更地価格から取り壊し費用を控除して求めることになり、現行使用を前提とした場合とは鑑定評価の方針が違ってきます。
ちなみに不動産業者の話では、この今回の競売不動産、資金力のある業者なら8億円出すかもしれない、とのことですが、いくらで落札されるでしょうか?興味深いですね。
占有権のついた土地の鑑定評価
占有権のついた土地の鑑定評価は、その使用権原が無権利であった場合、その占有者に専有物の撤去を請求費用分を控除した価格になるのが一般的な考え方になります。
先日、県道沿いに設置された所有者不明の大鳥居等を、市が強制代執行で撤去するとの記事を見ました。費用は約1100万円、建造物の規模等を考えると高いと思います。
この大鳥居、高さ約12mで確認申請不要であり、1975年の建てられたこと以外は不明、とのことです。県道等の官地に建っているのなら、建築時点に土地使用契約は結ばなかったのでしょうか。大鳥居という特殊な建造物で所有者不明、というのも不思議に感じました。
今回のような公道に鳥居や石柱、石灯篭などが建っているケースがありますが、どのような扱いになっているのでしょうか。一度、調べてみたいと思いました。
鑑定評価と地歴調査のお話
先日、ネットで江戸時代の処刑場跡地に建つホテルに霊が出るとの記事を見ました。霊感の強い人には成仏できなかった霊が見えたそうです。
不動産の鑑定評価を行う際、対象不動産とその周辺の地歴調査を行います。その際、資料として閉鎖登記簿、過去地図、必要な場合には過去の航空写真や過去の地形図などを使用して、地歴を調べます。但し、資料の収集には限界があるので、過去地図のある戦後以降の地歴を把握することが限界の場合が多いです。かなり前、ある地方で聞き取り調査をした際、対象不動産が屠殺場だったことがありました。山間の昼間でも暗い土地で、そこに向かう細い道は、牛や馬とそれを引く人が通れる広さにしたそうです。
現在は、名古屋でも江戸時代の地図などを見ることは可能なので、対象不動産がその当時どのような用途で使われていたかは知ることはある程度できますが、その当時の用途を鑑定評価額に反映させることはなく、また、あまり意味のないことだと思います。
もちろん、前記の屠殺場跡地は土も汚れていますし、市場性が著しく劣ることから相当の減価が発生しました。売却目的の鑑定評価でしたが、結局売れなかったと記憶しています。
線路の横の土地の鑑定評価
最近は高架上を通ることが多くなった鉄道ですが、市街地から離れた地域では線路の横に家が建っていることがあります。私の子供の頃住んでいた地域も、名鉄線の線路が通っていて、その線路横に家が建っていました。
線路の横に問題としては、騒音や振動などがありますし、踏切が近い場合などは警報機の音なども気になりそうです。私は遭遇したことはありませんが、線路の横の土地の鑑定評価に当たっては、何等かの減価が生じることになると思います。
電車マニアなどを除いて、あえて線路の横に住もうという人は少ないと思いますが、RC造などにして振動を抑える、防音窓にして騒音を抑える、などの工夫をして快適に生活することは可能かもしれません。
がけ地を含む土地の鑑定評価
先日の大雨は全国に大きな被害をもたらしましたが、がけ地の斜面を支える擁壁が崩れる被害も相次ぎました。
京都で崩落したがけ地の擁壁は、約50年前に造成された住宅団地の端で、玉石済みの上にコンクリートブロックの積み増しで、長年、基礎に負担が掛かっていたようです。水抜き穴もなく違法建築の可能性が高く、工事時期も不明、今回の大雨で崩落が起きました。
崩落が起きた地域は都市計画区域外、宅地造成区域外であり造成許可も不要、建築確認申請も行っていないと思われます。
がけ地を含む土地の鑑定評価は、そのがけ割合やがけの傾斜度、擁壁があればその維持管理や補修の状態を調査して行います。今回のような違法の可能性の高い擁壁の場合、有効利用できる土地の価格から既存擁壁を取り壊し費用及び、擁壁の再工事にかかる費用を控除して求めることになります。おそらく今回のケース、土地価格が低い場合、鑑定評価額もマイナスになると思われます。
がけ地の鑑定評価は、何件か遭遇しましたが、中々難しい評価になることが多いです。
飛び地の鑑定評価額
先日、ネットで東京都渋谷区と港区の境のある飛び地の記事を読みました。このケースは同じ東京都区部内の飛び地ですが、練馬区の西大泉町は、埼玉県新座市に囲まれた飛び地になります。
練馬区西大泉町の場合、県をまたいだ飛び地であり、上下水道をはじめ行政サービスを受ける際、解決する問題は出てくると思います。おそらく、費用負担することで、埼玉県新座市のサービスを受けることになると思います。
以前、私も飛び地の鑑定評価にあたり、問い合わせを受けたことがあります。大きな緑地公園で分断され、市をまたいだ飛び地でした。この土地は、現況、道路敷の緑地であり、上下水道はなし、共用をうけることも難しい土地でした。飛び地の解消を目的とした公共の買収でしたが、土地面積も狭く、妥当な鑑定評価額が付けられていたと思いました。
また、名古屋市ですと市街地の中に区界がある地域がありますが、商業地の鑑定評価の場合、需要者である法人の選好性を考慮し行政間格差をつけることもあります。法人は、営業上、所在地にもこだわりますから。
飛び地の鑑定評価、やはり難しい評価になることは間違いなさそうです。
« Older Entries Newer Entries »