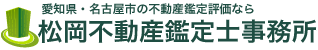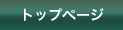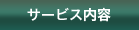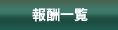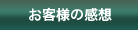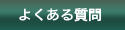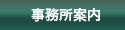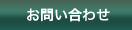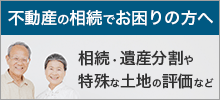Archive for the ‘不動産の価格’ Category
地価40億円の土地と再開発のお話
大規模再開発が続く東京で、今年2月に新たな再開発計画が竣工しました。場所は東京の大手町1丁目、周辺の土地の価格は地価公示価格で1坪訳9091万円だそうです。
その開発計画ですが、平将門の首塚を残す形で計画されているそうです。何でも、過去、このような開発計画が起こる度に事故が多発し、一部は強化ガラスで保護されています。ちなみに、その首塚の広さは約44坪、公示価格ベースで40億円強になります。
今回のような大規模な再開発の場合、期間も長期に及びますし、工事期間及び開業後の安全を考慮したものではないかと考えられます。
このような畏敬の念から残されているものとして、今回の首塚の外、ご神木があげられます。大阪や名古屋でも、ご神木を残す形で道路の整備を行った場所があります。
そういえば、リニモ新幹線の工事に伴い移転されることが決まった名古屋市中村区の椿神社ですが、ご神木を伐採する業者が決まったと聞いたことがあります。神社の移設の際には丁重にお祀りして、無事に工事が終わることを祈っています。
部屋の間取りと不動産価格の関係
先日、ネットでおかしな間取りについて書かれた記事を見ました。お風呂やトイレの入り口の前に洗濯機置き場があったり、幅約90cmの4畳の廊下の部屋があったり、2.5畳の三角形の部屋だったり・・、家の形状から苦肉の設計だったのでしょうか。
建物がこのような特殊の間取りの場合、当然、市場性は劣ることになり不動産価格は安くなります。リフォームで修正できるのであれば、その分の費用+アルファが減価額の目安になると思います。
また、家族向けの建物の場合、浴室やトイレは必要として、LDKと個室(寝室)の数と広さはチェックポイントになると思います。なので、一般的なエンドユーザーを需要者とする建売住宅の間取りは、汎用性の高い使いやすい設計にすることが多いです。
不動産の鑑定評価をしていて、前記のような特殊な間取りに遭遇したことはありませんが、思わず驚くような間取りを見てみたいと思いました。
名古屋北エリアのマンション価格
名古屋北エリア(北区、西区、守山区)は、エリア的には名古屋市北部に位置していますが、最寄りの鉄道路線も地下鉄名城線、同鶴舞線、名鉄名古屋本線、同瀬戸線と多岐に渡っており、代替性及び競合性は薄い印象があります。
その中でも騰落率20.7%と圧倒的な1位は、名古屋市西区の「栄生駅」でした。栄生駅は、名鉄名古屋駅の隣駅であり、名駅地区の北の外れに位置しています。名駅地区のマンション価格高騰の影響が、栄生駅まで波及したと思われます。
その他の特徴としては、名鉄瀬戸線沿線の「瓢箪山駅」が2位(5.8%)、「清水駅」が4位(4.0%)に入りました。瓢箪山駅は急行停車駅であり、栄への利便性が好まれたと考えられます。清水駅は、北区にありますが、東区と隣接しており、こちらも栄への利便性に優れています。
今回の結果、瓢箪山駅の2位は意外でしたが、マンション価格上昇が主要路線以外の郊外まで波及していることを示す結果となりました。
奥が深い不動産のお話
昨今の金融緩和の影響で、個人でも不動産投資をやる方が増えてきました。特に、今回の新型コロナウィルス感染症による無利子融資を利用して、不動産投資をやろうという事業者の方も見えるようです。
先日、ある集まりで税理士や司法書士の士業の方と話す機会がありました。実際に不動産投資をやられている方もおり、相当、知識と経験を積んでおられる印象でした。ただ、会話の中で、断片的な知識と経験に振り回されている、と感じたことがありました。最近は、不動産投資などのハウツー本も多く出回り、簡単に知識を得ることができますから。
不動産は奥が深く、不動産鑑定士をしている私でも迷うことが多くあります。もし、不動産投資や売買などで不安を感じることがあれば、身近な不動産鑑定士にご相談することをお勧めします。そうすることで、かなりの確率で大きな失敗を避けることが可能となります。
駅距離と不動産価格との関係
過去に何度も同じテーマで書いたと思いますが、今回も駅距離と不動産価格との関係を書きたいと思います。不動産の価格は価格形成要因が複合的に関連して掲載されますが、その中でも大きな要因の一つに最寄り駅からの距離があります。最寄り駅から近いと、通勤や通学便利ですし、買い物などの用事で都心に出るのにも有利です。なので、駅から近い土地は需要が多く、価格も高くなります。
もちろん商業地であれば、駅には通勤や通学客が集まってくるので収益性が高く、こちらも土地の価格は高くなります。容積率や道路などの条件が良ければ、共同住宅などの複合建物の想定も可能となります。
最近、新型コロナウィルス感染症の影響によるテレワークの普及で、需要者が重視する点が、駅距離ではなく居住環境や建物に変わった、との声が聞かれます。このような記事のほとんどがアンケート結果に基づいているようですが、実際のところはどうなのでしょうか?
私は、最近の駅距離を重視しない傾向は、一過性のものと考えています。駅から遠いところは値ごろ感があり、テレワークのみに徹するならお買い得かもしれませんが、駅から近くてもテレワークはできますから。
駅距離と不動産価格との関係、実際の不動産の取引から分析した正確なデータが望まれるところです。
定期借地権付きのマンションの鑑定評価
マンション(区分所有建物及びその敷地)の鑑定評価は、作業量が多く時間のかかることが多いです。そのマンション(区分所有建物及びその敷地)ですが、土地部分の使用権が所有権の共有持ち分である場合と定期借地権である場合があります。当然、所有権の方が強い権利ですし、定期借地権の場合、通常、解約期間の満了時には建物を解体し、更地にして返還することになるので、立地や建物の仕様等の条件が同じである場合、定期借地権付きのマンションの方が鑑定評価額は安いことが多いです。また、通常、区分建物の所有者は地代の支払い義務がある代わりに、固定資産税等の支払いは不要となります。
この定期借地権ですが、マンションの場合は契約期間が長期となることが多いですが、借地権の残存期間が短い場合は、その点を考慮した鑑定評価となります。但し、建物の状態も良く、地主が十分な地代を得ている場合などは、定期借地契約の契約期間が延長される可能性も否定できません。
地価上昇が続く昨今、事業用定期借地権で建てられた店舗など、契約満了時に終了しているケースが多いのですが、将来、契約満了時に経済環境が悪化している場合など、定期借地契約の契約期間が延長されるケースも出てくるのでは、と思います。
建築確認がない不動産の鑑定評価
不動産、建物の売買の場合、通常は契約の際、権利証とともに建物に関する書類(確認済証や設計図書)を売り主から引き継ぐことになりますが、古い建物や転売(前の所有者が紛失してしまった)の場合、これらの建物書類がない場合があります。
このような建物の鑑定評価を行う場合、書類の有無が鑑定評価額に影響を与えるかが問題となります。私も何度か書類のない建物の評価に遭遇しましたが、建物がかなり古く価値ゼロであったため、減価は行いませんでした。対象建物が築浅物件で価値が残っている場合は、何等かの減価を行う必要があると思います。
もちろん、調査によって違法建築物であるとわかれば市場性減価、場合によっては適法な建物に戻す費用や除去費用を控除して鑑定評価額を求めることになります。
建物の鑑定評価額は、確認済証はもちろん設計図書や請負契約書等書類の有無で精度が違ってきます。鑑定評価を行う際は、依頼者に可能な限り書類を準備して頂くようお願いしています。
名古屋南エリアのマンション価格
名古屋南エリア(昭和区、瑞穂区、熱田区、南区、緑区、天白区)は、私が地価公示を担当しているエリアとほぼ重なっており、地価変動率については精通しているところになります。
このエリアのマンション価格ですが、1位「鳴海駅」(+12.7%)、2位「妙音通駅」(+5.2%)、3位「御器所駅」(+3.8%)、4位「南大高駅」(+3.4%)、5位「神宮前駅」(+2.9%)という結果となりました。二けたを超える騰落率は1位の鳴海駅のみでした。鳴海駅は名鉄名古屋本線の急行停車駅であり、名古屋駅まで15分という利便性が好まれたようです。
この結果の特徴としては、1位の鳴海駅と5位神宮前駅が名鉄名古屋本線沿線、4位の南大高駅がJR東海道本線沿線と、地下鉄駅以外の駅が3つ入りました。また、3位の御器所駅周辺は、ここ数年地価上昇が続いており、マンション価格も上がりすぎていたことを反映した騰落率になったと思われます。4位の南大高駅周辺は、土地区画整理事業の影響もあり、マンション価格の上昇を反映した結果と思われます。
1位の鳴海駅周辺、地価は落ち着いていた印象ですが、マンション価格の上昇から推測するに、地価も上昇しているとみてよさそうです。
名古屋西エリアのマンション価格
最近、中古マンション価格の上昇が激しいです。私の知り合いも、新築で買った値段よりも200万円も高く売れたそうです。
名古屋市の西エリア(中村区、中川区、港区)のマンション価格ですが、やはり地価上昇の激しい中村区、特に名駅周辺のマンションの上昇が激しいです。マンション情報サイト「マンションレビュー」のデータによれば、5年前の価格との比較で、1位「亀島駅」(+21.5%)、2位「国際センター駅」(+15.2%)、3位「名古屋駅」(+10.8%)という結果となりました。1位から3位まで二けたを超える騰落率となりました。
考えられる理由ですが、マンション需要の増加はもちろんですが、地価や建築費の上昇で新築マンション価格が上昇し、その影響が中古マンションン価格に波及したと考えられます。建物の減価償却を考慮しても価格が上がる中古マンション、やはり普通の状態ではないと思います。
このマンションバブルの傾向、今回の新型コロナウィルス禍でどのような結果となるか興味深いところです。
飛び地の鑑定評価額
先日、ネットで東京都渋谷区と港区の境のある飛び地の記事を読みました。このケースは同じ東京都区部内の飛び地ですが、練馬区の西大泉町は、埼玉県新座市に囲まれた飛び地になります。
練馬区西大泉町の場合、県をまたいだ飛び地であり、上下水道をはじめ行政サービスを受ける際、解決する問題は出てくると思います。おそらく、費用負担することで、埼玉県新座市のサービスを受けることになると思います。
以前、私も飛び地の鑑定評価にあたり、問い合わせを受けたことがあります。大きな緑地公園で分断され、市をまたいだ飛び地でした。この土地は、現況、道路敷の緑地であり、上下水道はなし、共用をうけることも難しい土地でした。飛び地の解消を目的とした公共の買収でしたが、土地面積も狭く、妥当な鑑定評価額が付けられていたと思いました。
また、名古屋市ですと市街地の中に区界がある地域がありますが、商業地の鑑定評価の場合、需要者である法人の選好性を考慮し行政間格差をつけることもあります。法人は、営業上、所在地にもこだわりますから。
飛び地の鑑定評価、やはり難しい評価になることは間違いなさそうです。
« Older Entries Newer Entries »